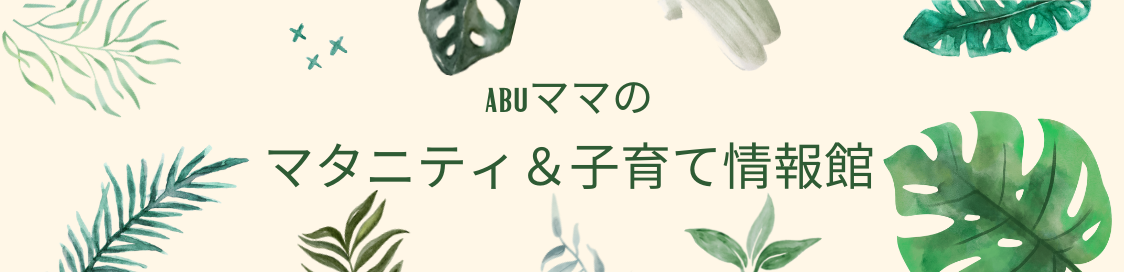Contents
妊娠性鼻炎の対処法②ダニ

通年性アレルギー性鼻炎のなかでも特に悩まされている方が多い、ダニ。ダニ対策には、室内を衛生的に保つ+ダニが嫌がる環境に整えることが鉄則です!
寝具からダニを追い出す
実は、家の中のダニ対策で最も重要なポイントが『寝具』。寝具には、ダニの好物である人の皮膚やフケが沢山あったり、適度な湿気・温度が保たれていたりと、ダニが大増殖する条件が揃っているのです。

布団のダニ対策は“日光で干す”のが一般的ですが、実はこれでは不十分…。
ダニは50℃の熱にさらすと20~30分で、60℃の熱では一瞬で死滅します。しかし、ダニの死骸もアレルゲンとなるため、死骸をきちんと掃除機で吸い取ることも欠かせません。
そこで活用したいのが、布団乾燥機と布団用クリーナー。布団乾燥機を使って布団を高温乾燥させる+掃除機でしっかり吸い取ることで、ダニの退治+除去を簡単にできちゃいます!
なお、ダニを通しにくい素材・生地を使った寝具に買い換えるのもおすすめです。
こまめに、かつ丁寧に掃除機・拭き掃除をする
こまめな清掃も大切です。
ただここで注意したいのは、掃除機を勢いよくかけると埃が巻き上がってしまうこと。埃にはダニの死骸やフンなどが混ざっているため、余計にアレルギーが悪化してしまう可能性もあります。
そのため、掃除機はなるべく丁寧にゆっくりとかけましょう。また、掃除機を使わずに雑巾・掃除用のワイパーなどで拭き掃除をするのもおすすめです。
湿気を逃す
ダニは高温多湿の環境を好むため、特に梅雨時期には除湿器を活用して湿度を50%程度に保つことも欠かせません。
また、カーペットや布ソファーなどは湿気を吸いやすいことから、ダニが繁殖しがち。そのため、カーペットは布団乾燥機などを使って湿気を除去する、布ソファーはこまめに掃除機をかける必要があります。または、
- カーペット⇒フローリング
- 布ソファー⇒革ソファー
妊娠性鼻炎の対処法➂ペットの毛・フケ・尿・唾液など

アレルゲンは極力遠ざけるのが鉄則ですが、家族の一員であるペットはそう簡単に手放せるわけではありません。これまでと同様に一緒に暮らしていくには、さまざまな工夫が必要です。
屋外飼育に切り替える
ペットのアレルギー対策で重要なことは、アレルゲンとなるペットの毛やフケをなるべく吸い込まないようにすること。
そのためには、可能であれば屋外で飼育するようにしましょう。ペットを室内に入れないことで、アレルゲンが宙を舞ったり、カーテン・カーペット・寝具などの布製品に付着するのを防げます。
もし屋外飼育が難しいようであれば、最低限ペットが入れないスペースを確保しておいてください。例えば、多くの布製品がある「リビング」・一日のほとんどを過ごす「寝室」などにペットを入れないのがおすすめ。また、寝具カバーをアレルギー対応製品に替えるのも有効です。
室内の布製品を減らす
室内で飼育する場合には、そもそもペットの毛やフケが付着しにくい環境にしておくことも大切です。
カーペットはフローリングに替える、布ソファーには毛が付着しにくいカバーを掛けるなど、布製品を減らす工夫を施すことでアレルギー症状の軽減に繋がります。
空気清浄機を設置する
空気中に漂うペットの毛やフケを除去するには、空気清浄機を設置するのがおすすめ。特に、風量や集塵力が高く、ニオイ対策もできる「ペット用空気清浄機」を用意しておくと、さらに高い効果を期待できます。
また、なかには”天井埋め込み型”の空気清浄機なども販売されているので、省スペースで設置したい方はチェックしてみてください。
ペットや飼育環境を清潔に保つ
ペットの身体を清潔に保つことも欠かせません。定期的にシャンプーをすることで、アレルゲンとなるフケや汚れをしっかりと落とせます。また、こまめなブラッシングで抜け毛を軽減できるほか、ノミ・ダニなどの発見にも繋がります。
さらに、ペットの身体だけではなく寝床やトイレなどをこまめに掃除することも大切です。
なお、ブラッシング時は毛が舞い上がるので要注意。ブラッシング終了後は、隅々まで掃除をしておきましょう。
ペットと触れ合ったあとは手洗いをする
忘れがちなのが、ペットを可愛がったあとに手を洗うこと。
ペットの唾液や毛が手についた状態で目をこすったり、物を食べたりした場合、あっという間にアレルギー症状が現れてしまう恐れがあります。触れ合ったあとの手洗いは、習慣づけておきましょう。
まとめ

妊娠性鼻炎になってしまっても、自己判断での薬の服用は厳禁。アレルギー症状があまりにもひどかったり、なかなか軽減されない場合は病院に相談してみてください。
妊娠初期の場合は薬の服用を極力控えなければなりませんが、妊娠中期以降であれば“妊婦に使えるアレルギー薬”を処方してもらえるケースもあります。
産婦人科ではなく耳鼻科・眼科などに行く場合は、必ず妊娠中であること&妊娠週数を伝え、安全に使えるものを処方してもらいましょう。